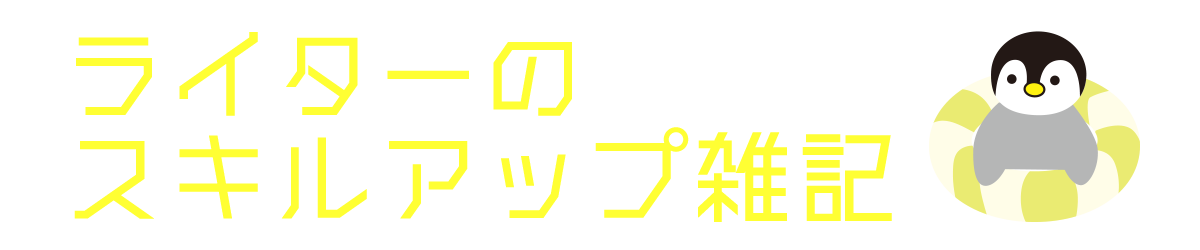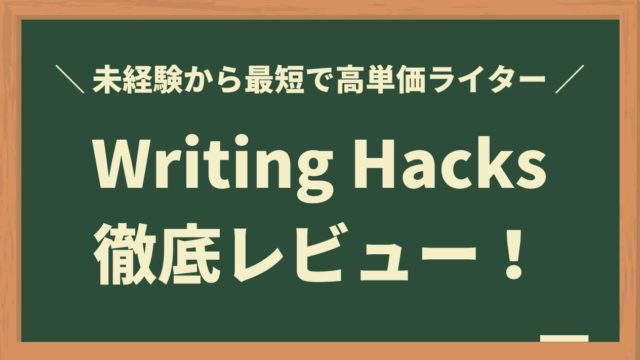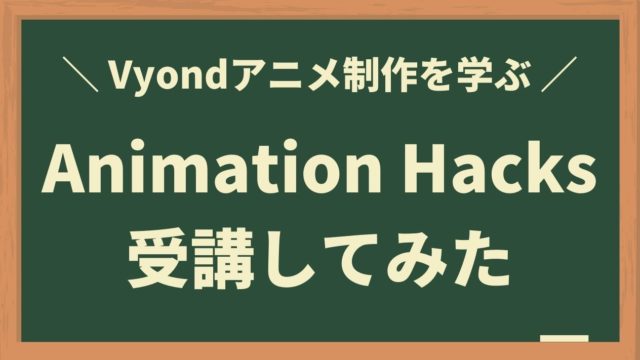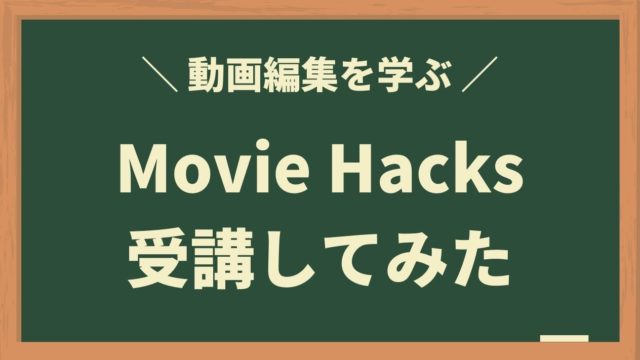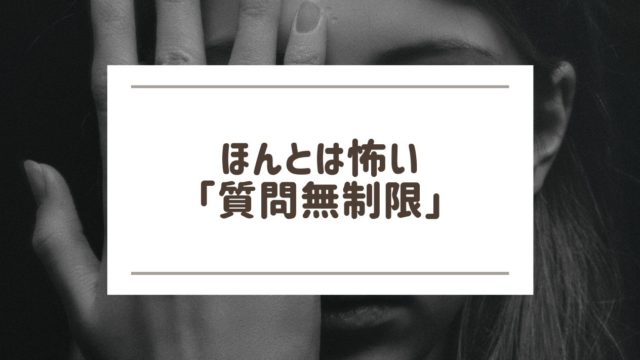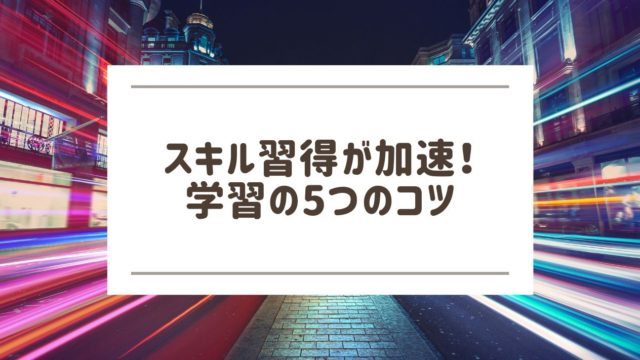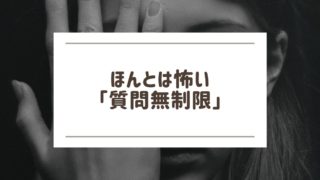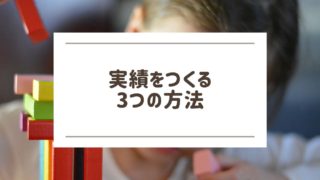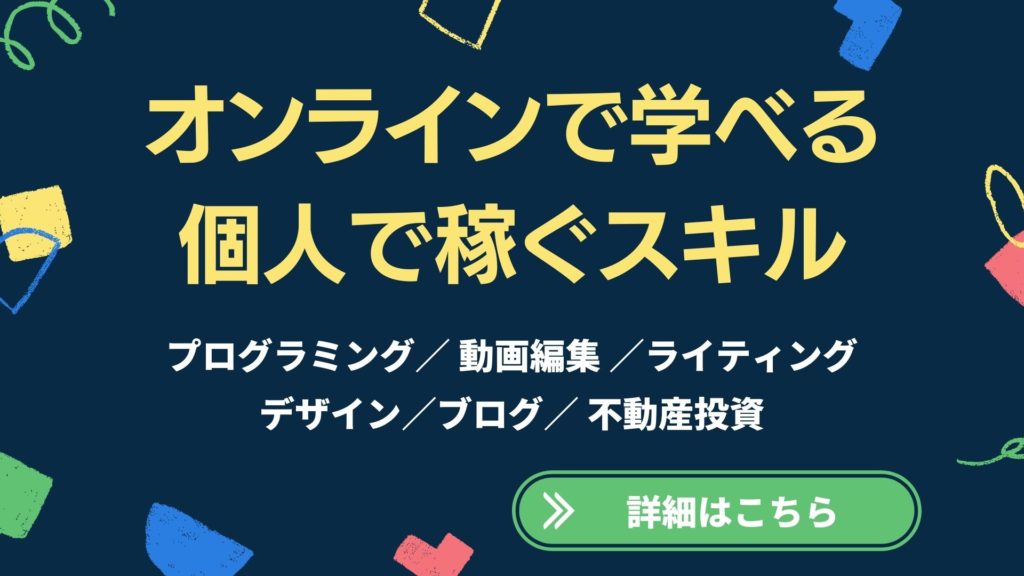こんにちは、ちな(Twitter)です。
先日に以下のツイートをしました。
【これまで勉強してきたこと】
①やめた・落ちた
・FP
・簿記
・宅建
・秘書検定
・公務員試験②受かった(でも使ってない)
・行政書士
・損保代理店試験③使ってる
・ライティング
・Webデザイン
・動画編集①②原因は、取ることだけ目標だったからです。③は、使うことが目標だったからです。
— ちな (@writer_china) April 7, 2020
挫折や失敗を含め、いろんな勉強を通して、実感したこと。
それは、
- 学習にはロードマップがある
- 勉強方法は使い回せる
といったことです。
うまくいかなかった時は、このロードマップのいずれかが欠けていました。
この記事は次のような人の参考になります
- これから勉強を始めたい
- 勉強方法を知りたい
学ぶ内容が何であれ、割と汎用できます。
【最初に】資格・教材学習に対する3つの誤解
本題に入る前に、勉強に対するよくある3つの誤解を紹介します。学習に入る以前に、ここにひっかかることがあります。
どんな誤解かと言うと、
- 資格なんか取っても無駄
- 受講さえしたら仕事にありつける
- 「満点」を取るべき
という3つです。
1つずつ詳しく見ていきます。
誤解①資格なんか取っても無駄→その思考が無駄
1つ目は「資格なんか取っても無駄」という誤解です。
これは半分その通りで、半分誤解です。
どういうことかと言うと、
- 勉強することが「目的」となっているなら無駄
- 勉強することが「手段」となっているなら無駄じゃない
ということです。
どんな資格もスキルも、使わないなら持ち腐れです。
自己PRとかでちょっと役立つことはありますが、それにしても学んだこと自体が活かされておらず、もったいないです。
逆に、資格合格を最終目標ではなく過程ととらえられるなら=手段ととらえられるなら、資格勉強も資格を取ることも無駄ではないです。
少し話がそれますが、資格名で「この資格は使える」「この資格はもはや使えない。オワコン」みたいなのも見かけますが、それも違うかなと思います。
確かに市場規模とか稼ぎやすさとか人気度は資格ごとに異なります。ぶっちゃけもはやAIがしたほうが良い仕事だってあります。
ただ、そんな中でも結局勉強したことを使って稼ぐ人は稼ぐし、稼げない人は稼げないです。
資格を取っても使えないと「需要が無かったせいだ」と他責で終わらせたくなるんですが、たぶんそうじゃないです。
資格が終わってるのじゃなく、「その資格さえ取ればそこそこ安泰だろう」という考えが終わってたんです。
勉強したことが無駄になったのは、どう使っていくか目標を立てなかった自分、稼ぐ工夫をしなかった自分の責任です。
(自戒)。
誤解②受講さえしたら仕事にありつける→自発的行動が必要
2つ目は「資格さえ取ったら仕事にありつける」という誤解です。
- この資格を取ったら独立できる(わくわく!)
- この講座を受講したら仕事が舞い込んでくる(わくわく!)
もしかすると実際そういう人もいるかも知れません。資格を取ったら即収入あったよ!みたいな。でも、再現性は極めて低いです。
そもそも「すぐ独立できた」とか「数日後に案件ゲットしたよ」という方は、以前から人脈づくりをしていたかも知れませんし、営業をかけていたかも知れません。
「今こんな勉強してます」と周りに伝えておくことも営業の1つです。
なので「資格さえ取ったら」「この講座を受講したら」という部分が誤解です。
絶対に自発的な行動が必要です。
勉強や学習というのは基本的に受け身です。何も知らないところから教えてもらうので受け身です。でもそこから「稼ぐ」とか「何かを成し遂げる」という部分は自分がするところです。
だから逆に「これさえ読めば稼げる」とか「この教材を見るだけで成功する」みたいな誘導には注意です。
「どこかにラクなショートカットがある」と思っていると、こういった罠にハマりやすいかも知れません。
誤解③「満点」を取るべき→「及第点」でOK
3つ目が『「満点」を取るべき』という誤解です。
たとえば行政書士という資格は、大きく「法令科目」と「一般知識」に分かれています。
合格基準は次のようになっています。
- 法令科目で122点以上(244点満点)
- 一般知識で24点以上(56点満点)
- 全体で180点以上(300点満点)
上記の通り、300点満点じゃなくて、6割取れば合格なんです。
ただし、各科目ごとの合格点に達していなければなりません。
なので「いかに高得点を取るか?」ではなく「いかにバランス良く学ぶか?」です。
こういう資格は多いですし、たとえば動画編集スキルだって同じです。
動画編集の案件は「カットとテロップ入れお願いします」というのが結構多いです。この条件が及第点だとしたら、合格(採用)はさほど難しくないです。だから応募するだけするべきです。
しかし「アニメーションもごりごり作成できて、なんならオリジナルBGMも創作できたほうがいい。だからもっと勉強してから応募しよう!」って先延ばししてたら、いつまで経っても稼げません。
もちろんできることは多いほうが、クライアントの要求に柔軟に対応できます。
でも「もっともっと」と高得点を狙うより、及第点でOKって意識のほうが、かえって良かったりします。
- 「及第点」はどこでしょう?
- 「高得点」が本当に求められていますか?
私自身「自分ごときが応募して良いのだろうか…」と尻込みすることが多々あります。「いや待てよ、早まるな!あれもこれも準備しなければ!」と身につけて武装したくなります。
そんな時は「とりあえず及第点ならおけ!」と思うようにしています。その後のことはあまり考えません。必要ならその時なんとかしてできるようにします。
この段落をまとめます。
- 資格なんか取っても無駄→その思考が無駄
- 受講さえしたら仕事にありつける→自発的行動が必要
- 「満点」を取るべき→「及第点」でOK
以上が、よくある3つの誤解でした。
次の段落からロードマップです。
勉強の進めかた7ステップ
いくつか勉強してみて私が「これがベストだな」と現時点で感じている勉強法はこちら。
- なぜそれを勉強するかを決める
- 無料でやってみる
- 有料でやってみる
- 勉強計画を立てる
- 勉強を習慣化する
- 勉強したことで稼ぐ
- さらに磨いていく
細かいところは人によってアレンジしていくと良いですが、本当にまったくの手探り状態なら、まずはこれをベースにして始めてみてください。
やっていくうちに「ここはもっとこうしたほうが良いな」という箇所が出てくると思います。その時は、自分用にカスタマイズしてください。
ステップ1.なぜそれを勉強するかを決める

ステップ1は「なぜそれを勉強するかを決める」、つまりゴール設定です。
私はこれまで本当にこれができていなかったです。
- 友人に誘われて宅建スクール行ってみた
- 法律詳しいとなんかカッコいいから法律を勉強してみた
- FPいつか役立ちそうだから勉強しとこう
こんなふうに「なんとなく」「いつか役立つかも?」と曖昧な気持ちで始めていました。
「これはこれで強みかなあ」と思うこともありますが、やはり目標やゴールは明確にしておいた方が良いです。
なぜ良いかと言うと、後半ステップ4で触れますが、勉強計画が立てやすくなるからです。
フルマラソンだってゴール設定せず走り出しても、ペースとか水分補給のタイミングとか分からないですよね。「きつい。疲れた。もうやめよう」って思うかも知れません。(フルマラソン未経験ですが…)。
ステップ2.無料でやってみる

目標を立てた勢いで「よし!決意は固まった!気になってたこの教材買おう!」とお金を出したくなるところですが、ワンクッション挟みましょう。
いわば見極め期間、お試し期間です。
これまた私がやりがちだったんですが「よし、やろう!」→「情熱のままに20万の教材買った!」→「うん、なるほど分からん!→「さよなら!」というルートです。
お金がもったいないです。
そうならないために、無料もしくは極めて低価格で学習を始めてみましょう。
「極めて低価格」というのは「最悪吹っ飛んだとしても仕方ないと思える金額」です。挑戦代みたいな。
手段はいろいろありますよ。
- YouTubeの無料チュートリアル動画で勉強する
- 書籍1冊買ってやってみる
- サンプル教材に着手してみる
「うん、好きそう。なんか、できそう」と小さな手応えを感じたら、次は有料でやってみましょう。
ステップ3.有料でやってみる

無料か?有料か?人によって意見が分かれるところですが、私はなるべく身銭を切るようにしてます。
もし自分が「やめよっかな…」って思った時に、「おい簡単にやめるな、もったいねー!」って自分が出てきてくれるようにです。
- 元を取るまで諦められない
- すでに支払ってしまったものを簡単に諦められない
聞いたことがある人も多いでしょう。
「サンクコスト」とか「埋没費用」と言われる心理効果の力を借ります。
ただこのサンクコストって諸刃の刃で、「諦めたほうが結果的に良かった」というケースもあります。ギャンブルとかこの心理効果が影響しますよね…。
だから、最初のステップ1「なぜそれを勉強するかを決める」がとても重要なんですね。
サンクコストに良い働きをしてもらうために、そもそもゴールは何だったかという話です。
ステップ4.勉強計画を立てる

ステップ4は「勉強計画を立てる」です。
このステップ4はステップ3と同時進行かも知れません。2と3の間かもですね。
- 無料教材を試す
- 「いける!」と手応えを感じる
- 勉強計画を立てる
- 有料教材に手を出す
この「勉強計画を立てる」の重要性は、行政書士教材の先生(LECの横溝慎一郎先生です)が再三、言っていたと記憶しています。
- ゴールを決め
- そのゴールに到達するために必要な勉強量を把握し
- 試験当日までの日数をカウントして
- 1日にどれくらい・何を勉強するかを決める
このフローで進めることで、巨岩に見えたゴールが小石サイズに細分化され、漠然としたプレッシャーが「やるべきこと」に変わってくれます。
ただ、資格勉強は「受験当日」という明確なゴール(強制)がありますが、動画編集とかWebデザインとかスキル勉強は、強制ゴールがありません。マイペースに勉強できる反面、計画を立てないと自然消滅してしまいます。
なので、自分で打ち立てる必要があります。
たとえば「3ヶ月後に5万円稼ぐ」みたいなものですね。
他人の結果は気にせず、最初は低めの目標を・具体的に立てるのが個人的におすすめです。
猪突猛進、猪突猛進!!!みたいな伊之助タイプは、ガツガツ高い目標もOKでしょうかね。
私は低め設定が性に合いますが、とにかく自分に合ったゴール設定をしましょう。目標は高い方が燃えるぜ!みたいな人はそうしたら良いと思います。自分の性分に合った設定であれば。
いずれにしても、期間・金額などゴールを決め、そのゴールにたどり着くまでのロードマップを細かくつくっておくことがこの後をラクにしてくれます。
ステップ5.勉強を習慣化する

ステップ4「勉強計画を立てる」で、すべきことが可視化できました。
後はそれを毎日続けていくだけです。
ここまでくると私は苦労しないのですが、この習慣化が苦痛…ここで挫折しがち…という場合があるかも知れません。
なので1つアドバイスですが、日常ルーティンの中に組み込むと、強制力が働いて割と習慣化しやすいです。
強制力のあるものの間に、勉強時間を入れ込むということです。
「ちょっと何を言ってるか分からない」状態なので、具体例を挙げさせてください。
私がフルタイム勤務しながら行政書士の勉強を毎日続けてた時のスケジュールです。
5:00 起床(強制)
5:00〜7:00 勉強(ここ)
8:30 出勤(強制)
超ざっくりですが、このように強制サンドイッチマンしました。
- 起床は、絶対起床しないといけないです。会社に行かないといけないから。
- 出勤も、絶対出勤しないといけないやつです。仕事があるから。
この2つは絶対しなきゃいけないことなので、この間に勉強を落とし込むんですね。
そうするとまるで間に挟まってるやつまで強制であるかのように、しれっと習慣化されっていくっていう不思議な現象が起こるんです。
まだ「ちょっと何を言ってるか分からない」状態だったら、ごめんなさい。
時間帯はなるべく朝、午前中です。
起床後は頭が働きます。逆に仕事終わりは、時間が確保できないことが多いです。1日働いたので、頭も疲れています。
なので、起床後の強制サンドイッチマンは割と有効でした。私には。
勉強を習慣の一部に変えたら、ゴール到達まで淡々と続けていくだけです。
下手に工夫とかしなくて良いです。
計画の遅れがあったら多少修正を加える程度にとどめて、余計なことに頭を使わず、心を乱さず、愚直に一歩一歩進めるのが良いです。
他人の進捗、周囲の喜怒哀楽、どうでも良いです。関係ありません。
ステップ6.勉強したことで稼ぐ
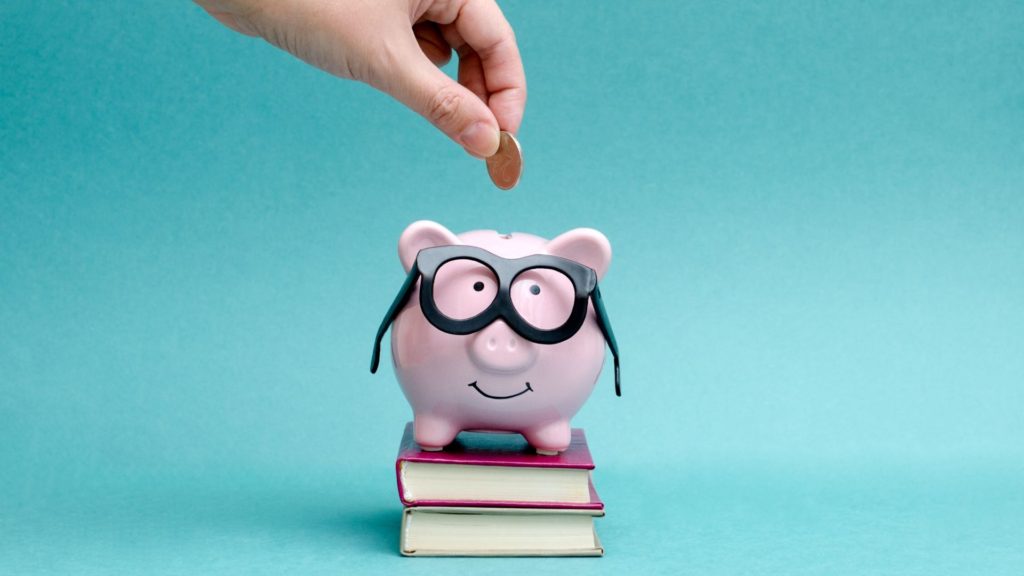
ゴール達成後の話になるので、ここから説明を簡略化しますね。
計画を立て、その通りに実行し、ゴールに到達したら、後は学んだことを使って稼ぐなり役立てるなりです。ここに来てやっと勉強の成果が発揮されるんですね。
ゴールに到達した後の達成感はとても強いものだと思います。それは成功体験ですので。
でも喜ぶだけ喜んで、勉強したことを使わないままと、忘れてっちゃうんですよね…。
ぱーっと喜んだら、ここまで勉強したことを使っていくと良いです。
ステップ7.さらに磨いていく

さらにその先の話になります。
勉強って、暫定ゴールを設けることはできますが、基本的には終わりのないものです。
仮に自分が「先駆者」だったとしても、磨いていかないとあっという間に後発に抜かれて、需要が減って、結果的に持ち腐れになることもあります。
挫折する3つの原因と対処法
ゴールを設定し、計画どおりに進めていても、挫折しそうになることがあります。
挫折につながる3つの原因は次のとおり。
- 他人と比べる【無意味】
- 「効率的にやろう」と考える【ありません】
- 途中で方法を変える【迷路の入り口】
対処法とともに見ていきましょう。
挫折原因1.他人と比べる【無意味】

他人と比べることは無意味です。
いえ、無意味はゼロって意味だからゼロじゃないですね。マイナスです。
他人と比較すると「自分は足りない」「もっと頑張らなきゃ…!」と不安に陥ります。すると、計画に乱れが出てしまいます。
計画が乱れると、ゴールまでの道筋が揺らぎます。
比べなくて良いです。ていうか、比べちゃ駄目です。
私もある資格の勉強をしていた時、他の人の「1日15時間勉強した」とか「模試で○点だった!」みたいな声に焦ることがありました。
なのでSNSは一切見ておらず、勉強仲間は作らず、休憩時間は勉強とは無縁のことをしていました。
挫折原因2.「効率的にやろう」と考える【ありません】

資格学校の先生が「近道はありません」とよく話していました。
書店で参考書を見ていても多いですよ、そういうタイトルやキャッチコピーが。
とにかく効率性を訴求してくるんです。
魅力的だし、実際そうだと思います。でもそれって「独学より効率的だよ」って意味なんだろうなくらいにとらえて、やっぱり自分でやるしかないです。
近道を探す手間がそもそも非効率だということもあります。
「ラクな近道はない」「1歩ずつ着実に進めば大丈夫」というマインドで大丈夫です。
挫折原因3.途中で方法を変える【迷宮へようこそ】
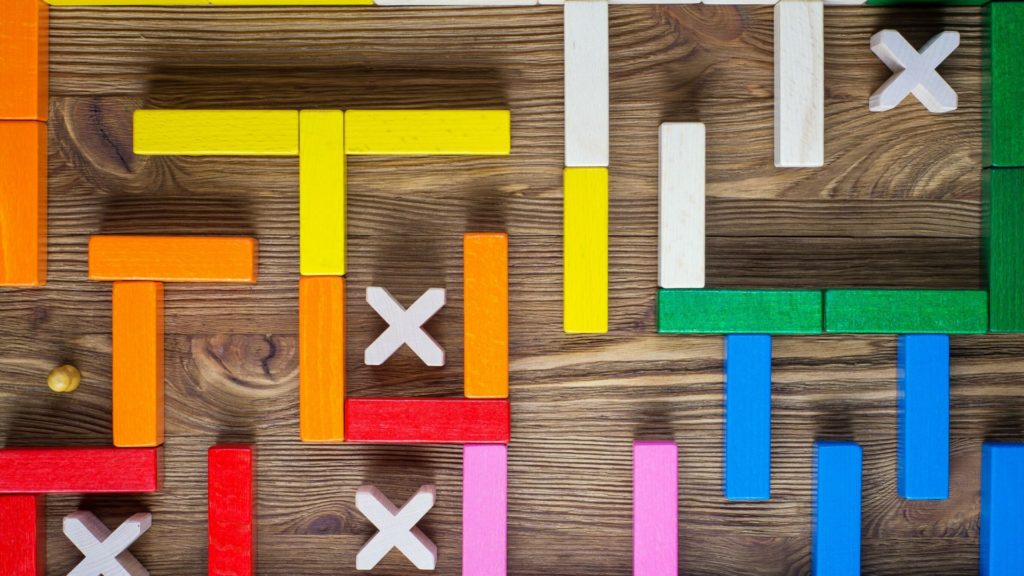
2つ目とつながる話ですが、教材やメンターをころころ変えることが挫折につながることがあります。
- 「今まで教材Aで勉強してたけど、教材Bのほうが人気だし、乗り換えようっと♪」
- 「C先生よりD先生のほうが人気だし、D先生にしようっと」
みたいなことですね。
これって根底に何があるかと言うと、他力本願なんですよね。
「他人が自分を引っ張り上げてくれるだろう」「これさえしてれば安泰だろう」みたいな考えがあって、そういう考えのままだと、結局うまくいかない気がします。
仮にそれで勉強を終えても、実務をするのは自分ですよね。想定外のこととか、トラブルとか、いろいろあると思うんです。
その時、他力本願の思考って役立ちません。
勉強の段階から「勉強するのは自分」ということを念頭に置いておくと、長い目で見たら自走力みたいなものが身につくんじゃないかと思います。
「このまま突き進んで良いのか?」とか「他の選択肢がベターだったんじゃないか?」とか不安になる気持ちはすごく分かります。
お金も時間も有限なので、無駄にしたくない気持ちもありますよね。
ただ、
- そこでガラッと方向転換することが本当の解決策なのでしょうか?
- 環境じゃなくて自分の意志を変えるタイミングなんじゃないだろうか?
ということを、考えてみて欲しいです。
まとめ:応用可!勉強の進めかた7ステップ
勉強方法は一度確立させてしまえば、将来ずっと使えます。たまにアレンジや修正を加えてブラッシュアップは必要かもですが。
何を勉強するにしても、フローはだいたい一緒です。
1度「これでうまくいった!」という経験があれば、挑戦に対するハードルがぐっと下がります。
だから、勉強すればするほどラクになります。自分用に自分でカスタマイズした勉強法を当てはめるだけなので。「これ勉強しよう」と思ったら、このフローに落とし込んであとは淡々と進めると良いです。
期間や難易度の差はありますが、基本的にそんな感じかなと思ったので、今回まとめました。
この記事は以上です。
お読みいただき、ありがとうございました!